篠原梵の百句
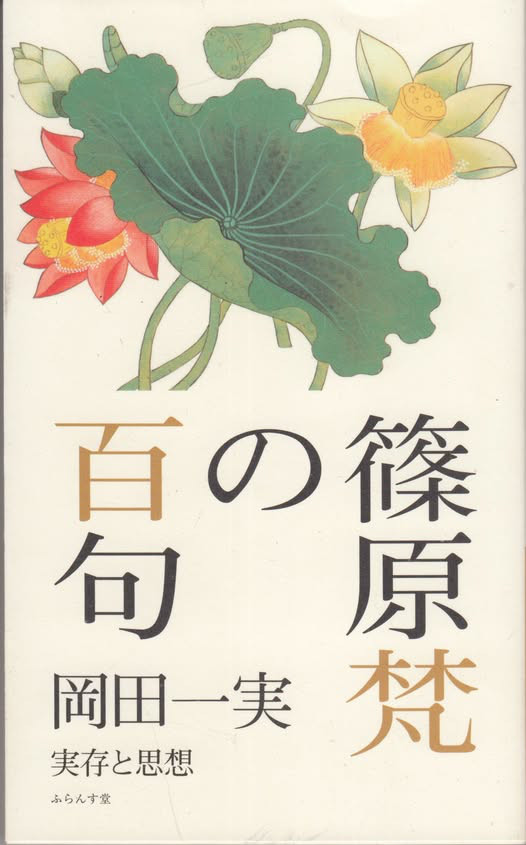
https://fragie.exblog.jp/33942941/ 【岡田一実著『篠原梵の百句』刊行!】より
雪柳。桜咲く季節は雪柳の白さもまぶしい。別名、小米花、あるいは小米桜というのもわかる。仙川の桜も大分花ひらいた。
今日はその桜のまわりで、「がんばれ能登半島! 復興へ とどけみんなの声」と題して、市民団体による「夜桜チャリティーコンサート」が行われるようだ。昼間通ったらスタッフの人が椅子を並べていた。帰りに寄ってみたいと思うが、多分わたしの帰る頃は終わっていると思う、なあ。。。
岡田一実著『篠原梵の百句』が出来上がってくる。
篠原梵(しのはら・ぼん)は1910(明治43)年に生まれ、1975(昭和50)年に没した俳人である。愛媛県松山市にうまれ。〈葉桜の中の無数の空さわぐ〉はよく知られている作品であるが、ほかの作品はほとんど知られていない。その俳人の作品百句を岡田一実さんが情熱をもって取り組まれたのが本著である。
わたしももっと読まれていい俳人であるとおもう。その鑑賞と解説をすこし紹介したい。
灯に読むにうしろさむざむ影の立つ 『皿』
梵は熱心な読書家であった。愛媛県立松山中学校時代、夏目漱石の作品に出会い、濫読の日々が始まったという。よって、読むことをテーマとした句も多く秀句も多い。〈爪先の冷えてねむれず読み継ぎぬ〉〈頭のみ日かげに入れて本を読む〉〈読みさして手をぬくめては寝つつ読む〉など。
掲句は自画像であろうか。第三者的な視点から本を読む人の後ろの影を捉えている。壁などにかかる影を〈立つ〉と把握する点が鋭い。「アパートの冬 三四句」。
手袋の手を挙げ人の流れに没りぬ 『皿』
別れの挨拶として手を挙げる。後ろ姿であろう。大きく腕を振らずとも、グッドバイの仕草であることは見ている者には伝わる。手袋の色・形が浮かんでいるように見える。しばらくはその手袋だけを目で追うこともできるかもしれない。しかし、やがて、それも人波に吞まれていく。
離別しきってしまう前の名残惜しさは、完全に一人となってからの寂寥感よりエモーショナルかもしれない。
没りぬ〉と人の流れに入ったところまでしか描かず、程なくそれが消えていくことを、読者に予感させるところに表現の冴えがある。「冬 二九句」。
星と星のあひだ深しや木犀にほふ 『雨』
星々の遠近は肉眼ではわかりにくい。何光年も離れた星と星が、肉眼では「隣の星」と平面的に把握されることも多かろう。星々を奥行きあるものとして捉えられるのは、宇宙についての知識があるからであろう。
掲句、その認識を〈あひだ深し〉と詩に昇華した。作中主体は地上から眺めつつも、宇宙的な奥行きを捉えたのである。木犀の花の強い香りが漂うことに、空間性を見出せるからこその発想であろう。嗅覚を使った身体的な実感が、知的なロマンと結びつき、詩情を得た一句である。「木犀」。
梵の命日は「木犀忌」という。
春の夜の闇より濃ゆき山に対ふ 『年々去来の花』
春、潤んだ空気が満ち、生命感が躍動する。その夜闇のなか、それ以上に濃い闇をもつものを発見する。山のシルエットだ。深い闇に対峙し、目を凝らす。漆黒に近い闇は見ている者を吸い込みそうだ。その先に何があるのかはわからない。真の闇をじっと見るのだ。無と向かい合うような時間が刻々と流れていく。
そのときの作中主体の胸中はわからないが、自我や存在を問い直すような、哲学的な思索に、自然と引き込まれることも大いに考えられる。
濃淡の甘やかな闇が、梵を包む。
篠原梵は、仕事人としては、中央公論社に入社してより「中央公論」の編集長、出版部長等など管理職を歴任し、出版社を設立するなど、出版人としておおいに活躍したようである。俳人としては、解説によると、
月刊「俳句研究」昭和一四(一九三九)年八月号「新しい俳句の課題」と題した座談会で、司会の山本健吉により中村草田男・加藤楸邨・石田波郷と並ぶ「人間探究派」の一人として括られ、梵の名は俳壇に深く刻まれることとなった。
とあり、「人間探究派」の一人であったことを、わたしはこの解説で初めて知ることになった。草田男、楸邨、波郷などに比して、岡田一実さんは記す。
梵はどうであったか。
反「ホトトギス」的であった臼田亞浪主宰の「石楠」に所属し、感覚や情感を知的に分析する方法をとる表現で頭角を現わしていた。梵の「人間探究」は他の三人と異質な意味をもつ。草田男、波郷、楸邨は句意の上で難解さが表出することも厭わず、「人間はいかに生きるべきか」といった個人の感情、憂鬱・不安・動揺・苦悩・個人的愛情を重視するロマン主義的な文学的意義深さをめざすような作風を模索していた。これに対し、梵の句は措辞が平明で、かつ、そういった文学的意義深さを解き放つ実存主義的な作風を模索していた。「実存」とは、「個的で具体的なあり方をした有限な人間の主体的存在形態」である。梵は人間の内部や生き方ではなく、モノ・コトを一回性の高い一つの契機として捉え、非-メッセージ的にその不思議と諧謔を深耕する方に「探究」を向けたのである。
「梵の句は措辞が平明で、かつ、そういった文学的意義深さを解き放つ実存主義的な作風を模索していた。」と岡田さんが解説をするように、篠原梵の俳句は、平明で構えのない作風である。詠まれているモノやコトがその背後に物語や感情が見え隠れすることもなく、それ以上でもそれ以下でもなくそこにある、そういうものとして詠まれ、読まれるものとしてある、ということなのだろうか。百句にふれてみておもったのだが、俳句は平易でやさしい表情をしているのだが、しかし、その俳句をじいっと見ているとある不思議さや面白さがあることに気づくのだ。たとえば、〈顔の高さまで部屋の中ぬくもりぬ〉という句、一見分かりやすい句に思えるのだが、「顔の髙さまで」、ウン? これはいったいどういうことなんだろうか、と思わず立ち止まってしまうのだ。さらに知りたい人は、岡田一実さんの鑑賞を読んでいただきたいと思う。
篠原梵は、俳句という短い形式の中で多くの可能性を探究した稀有な作家であった。俳句という短詩において多くの新しい地平を切り開いたにも拘わらず、その作品の多くが埋もれたままになっている。しかし、その作品たちは今日まで色褪せていない。梵の俳句には書き方の斬新さに加え、現代的なテーマも多く含まれる。今後、より多くの俳人や文学愛好者にその作品が愛されるように祈ってやまない。
影が斜めに横に斜めに独楽とまる 梵
おそらく篠原梵の俳句をこのように読み解いたのは岡田一実さんがはじめてだろうと思う。意欲的な取り組みをみせた『篠原梵の百句』である。
お客さまがひとりいらっしゃった。
石嶌岳さん。
「百句シリーズ」のなかの「皆吉爽雨の百句」の初校ゲラをもってのご来社である。
石嶌岳さんは、皆吉爽雨が創刊した「雪解」の同人である。
師・皆吉爽雨の俳句をいろいろな資料にあたって取り組み書き上げてくださった。
そして発見もあった。
それは、今まであまり知られていなかったことであるのだが、爽雨は、飯田蛇笏の選をあおいだ期間があったということ。
つまり「雲母」へ投句をしていたのである。およそ七年間。
そのことを石嶌岳さんは、今回の「百句」の執筆で資料をしらべていくうちに知ったのである。
石嶌さん曰く「爽雨の第一句集『雪解』の骨格のよろしさは、おそらく蛇笏の影響がおおいにあったと思います。そして切れ字が多いんです。七割がた切れ字を使っています」と。
「また、今回執筆してみて思ったことは、爽雨は生涯一句風ではないということ。目差しは一徹であったけれど、表現のあり方は変わっていったということ。たとえば中七の『や』どめから、そこを名詞で切っていくこと、それを定着させたのはおそらく爽雨ではなかったかと、思います」と。
実はこの「中七を名詞で切る」ことについては、わたしは石嶌岳さんにあるコピーをお送りした。
それは俳句文学館で調べものをしていたときに見つけた石田勝彦先生の「俳句朝日」に寄稿した文章だった。「わたしの転機の一句」というテーマで書かれた文章であり、「寒牡丹の一句」と題して
背山より今かも飛雪寒牡丹 皆吉爽雨
の句をあげて
「この句は中七の体言切れの句であるが、そこに倒置法が用いられている。語順から言うと、『今飛雪かも』、あるいは『飛雪今かも』となるところであるが、それを転倒させているのである。そこに叙法の雄勁とも言うべき動静が生まれている。巧緻を極めた叙法と言うべきである。(略)この句のような中七の体言切れの叙法のあることは知っていたが、古くはあまり見られない叙法で、普通は「や」で切る。したがって中七の「や」切れの叙法の変形とみることができるのであるが、この「寒牡丹」の句を見て、私ははじめてこの叙法に目が開かれたような気がした。それから私は爽雨俳句を勉強しはじめた。そして爽雨俳句には中七の体言切れの句が極めて多く、爽雨俳句の一特色と見ることができることを知った」
と書かれていた。ほんの一部を抜粋したが、「切れ」ということへの深い洞察のあるいい文章だった。
すぐにコピーをして石嶌岳さんに送ったのだった。
石嶌さんは喜んでくださって、さっそくこの「百句」にこの一節を入れられたのだった。
岡田一実著『篠原梵の百句』刊行!_f0071480_20532150.jpg
石嶌岳さん。
余談であるが、水原秋櫻子と皆吉爽雨はとても仲良しだったと教えてもらった。
そのわけは、ふたりとも「熱狂的な(?)アンチ巨人」。水原秋櫻子は、西鉄ライオンズ(いまの西部ライオンズ)の、皆吉爽波は国鉄スワローズ(いまのヤクルト)の、それぞれ大ファンで、「アンチ巨人」で意気投合したお二人は、俳人協会の会長(秋櫻子)と副会長(爽雨)をされていた時代には、家もちかくということもあって帰りはいつも一緒に仲良く帰られたということである。
そんな良き時代でもあったのだ。
6月29日は皆吉爽雨の忌日。
それまでには刊行しましょう、ということに。
https://note.com/chika158cm/n/nfe2a317d475a 【岡田一実 『篠原梵の百句』】より
ふらんす堂の百句シリーズより。
篠原梵の句は新鮮で面白い。そして岡田一実さんの鑑賞がいい。梵の句を的確に読み解いている。そして文章がとても美しい。百個ある鑑賞文のすべてが素晴らしくて驚く。
自分もいつかこんな鑑賞文が書けたらと憧れる。
ドアにわれ青葉と映り廻りけり 『皿』
硝子張りの回転ドアを通る状景であろう。硝子が鏡のようになり、自分の像と茂りの色濃き青葉が一緒に映る。そして、それが廻る。
「廻しけり」ではなく〈廻りけり〉とした措辞が、作中主体である〈われ〉の主体性を差し引いた表現になっている。ドライな眼差しと共に、コントロールの及ばないまま〈われ〉が連れていかれるような、仄かな不穏さも読者に感じされる。都会的でモダンな表現である。「丸ノ内界隈 二五句」。
岡田一実『篠原梵の百句』6−7頁
篠原梵は句集の名前がいい。第一句集が『皿』、第二句集が『雨』。ちなみに『皿』は愛媛の山「皿ヶ嶺」の名を由来とするらしい。(梵は山好き。)
