ひかりからかたちへもどる独楽ひとつ 神野紗希
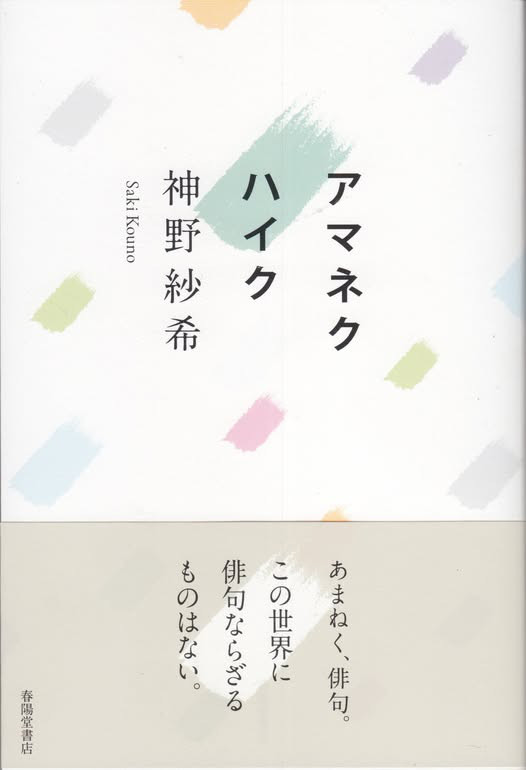
http://www.tokorozawa.saitama.med.or.jp/machida/koma-st01.htm 【こまの話】より
ここのお話は小川清実著こどもに伝えたい「伝承あそび」「こま」より発行者服部雅生氏(萌文書林社長)の許可を得て引用したものです。
「コマ」を漢字で書くと「独楽」となります。大人も子供もコマを回すことには夢中になります。現在でも、正月に子供達が遊ぶおもちゃの一つとなっています。コマは相当古い時代から大人も遊ばれているものです。現在残っている最古のコマはエジプトで発掘されたもので、紀元前2000年から紀元前1400年ごろのものということです。本当に長い歴史を持っています。「単なる子どものおもちゃ」とはいえない存在だと思います。
こまの歴史
それでは、日本のこまの歴史をみてみましょう。中田幸平(注1)によれば「独楽」という名は紀元900年代のはじめに書かれた『和名抄(わみょうしょう)』に「古末都玖利(こまつぐり)」とあるのがもっとも古いと述べています。
「古末(こま)」というところは他に「高麗(こま)」とも書かれました。これは中国から高麗(こま:朝鮮)を経て、日本に伝わったことからつけられたと考えられます。 また、「都玖利(つぐり)」とは、こま本来の呼び名で、ツグムリともツグリともいわれ、円を意味しています。 ツブラにも通じています。これらがいつのまにか略されて「古末」になったのではないかというのが中田の推論です。
古代のこまは宮廷の儀式としてもちいられることがほとんどでした。専門の独楽びょう師(儀式の際にこまを回して吉凶を占う人)がこまを保管し、神仏会(しんぶつえ 注2)や相撲節義(すもうせつぎ 注3)の余興として、紫のひもをつかって厳かに回したものでした。
古代の神儀性が薄れたこまが、だんだん貴族階級の大人の遊びとなり、実際に庶民の子どもたちの手に入るようになったのは、およそ300年後の江戸時代になってからです。江戸時代のこまは、無性独楽(むしょうごま)といわれ、貝をむちやひもでたたいて回すものでした。これは後のバイ独楽(ベーゴマ)です。
寛文年間に丸木を八角に削ったこまが登場しました。 八方独楽(はっぽうごま)と呼ばれ、もとは中国のもので、はじめは四角面ひねり独楽でした。 遊び方は回転がとまったときにでたこまの表面の文字で双六(すごろく)の進退を決める、サイコロと同じものでした。日本ではその後、六角となって使われるようになりましたが、六角面の表に「南無分身緒仏(なむぶんしんしょぶつ)」と焼き印をしていたために、遊び道具としては不似合いなものでした。 元禄時代になると、この六角に六歌仙(注4)などの絵入りのものやお花という人物を中心に5人の男女名を書いた独楽がでました。これはお花独楽と呼ばれました。 再び八角面も出て「春夏秋冬花鳥風月」の文字や絵入りのものがでました。これらの八方独楽は、単に回転を楽しむこまではなく、あくまでも双六の進退を決めるためのサイコロ的なものだったり、他の要素を楽しむためのものでした。
そこに回転そのものを楽しむこまが現れました。 唐独楽というもので、空鐘(とうごま)とも呼ばれました。木製の円筒の上下をふさぎ、胴に竪穴を開けて、中心に串状の心棒を入れたものです。回転させるとゴンゴンと鳴るので、ゴンゴン独楽ともいわれました。
回転の魅力をさらに伝えるこまとして、博多独楽が登場しました。博多独楽は心棒が鉄製で丈が高く、回転寿命が長かったのです。回し方が簡単なわりには、掌(てのひら)、棒先、横に張ったひもの上など、どこでも回り、独楽の曲芸のおもしろさがありました。 残念なことに、博多独楽の流行した場所が風紀上良くないところだったために、幕府が禁止令を出したのです。そのため回転をたのしむために、博多独楽に代わってバイ(貝)回しが流行しました。 このバイ回しは子どもだけの遊びになりました。
その後、天保年間には、子どもたちに鉄胴独楽が流行しました。鉄胴独楽は、木製の胴に厚い鉄輪をはめ、鉄の心棒を入れた、頑丈なものでした。 双六用の鉄胴独楽を交互に打ち当てて遊ぶケンカ独楽というゲームが寛永(かんえい)2、3年ころから流行しました。 はじめは、ただ当てるだけでしたが、次第にあいての独楽を激しくたたきつける方法に変化していき、子どもたちは相手の胴を打ち割るために、心棒の先をますますとがらせていきました。
明治時代の中頃に、ブリキ製の独楽が作られました。日露戦争後にはじめて作られたのは、ゴンゴン独楽(鳴りゴマ)でした。江戸時代に木や竹で作られた唐独楽は、ブリキ製になりました。胴の穴が1個と2個の2種類あり、穴が1つのこまはピーと鳴り、穴が2つこまはポーと鳴るものでした。その後は、押しゴマ、無線自動ゴマなどがどんどん作られていきました。
回転の魅力 と 戦いのおもしろさ
こまと遊ぶことは大人も子どもも楽しいことです。 こまの魅力は回転にあるといえるでしょう。 単にくるくると回転することがおもしろい。 幼い子どもは、こまが回転するのを見ていいると、自分自身も回転してしまいます。 子どもがこまになってしまうのです。 この体験の感覚がいつまでも忘れられず、こまの回転を見ていると、同時に自身のイリンクス(めまい)を感じているのではないかと考えられます。
こまそのものの回転を追及するだけでも相当楽しいものですが、やはり、最も人の心をワクワクさせるのは、こまを使って戦わせ、他人のこまを奪うことにあります。こまの中でもベーゴマがこの種の遊びの頂点にあったと思います。
注1) 中田幸平 「日本の児童遊戯」を昭和45年に著した。コマについて詳しく述べている。
注2) 神仏会 大勢の人が寄り集まって行う神事や仏教の行事
注3) 相撲節儀 相撲は現在では単なる協議k職業的興行物と考えられているが、本来は神事と関係深いものだった。
宮廷では初秋の行事として相撲節儀が行われていた。
諸国から優秀な人を集め、宮廷を中心にして国を東西に分け、その勝敗でいずれが豊年であるかを占っていた。
注4) 六歌仙 平安時代初期の歌道に優れた6人。
在原業平、僧正遍照、喜撰法師、大伴黒主、分屋康秀、小野小町
http://www.tokorozawa.saitama.med.or.jp/machida/komatohaiku.html 【独楽と俳句・短歌】より
独楽を詠んだ俳句や短歌等を集めたものです。句集や新聞、雑誌などで目にとまった句の解説文は主にそれぞれの句に紹介されていたものを使わせて戴きました。
わが夫の趣味は世界の独楽集め バリで竹独楽見つけ悦ぶ 町田のり子
2004年8月、バリ島へ旅行した際、タクシーを乗り回してやっと独楽を見つけた時の情景を詠んだ妻の歌。これが独楽に関する俳句・短歌を蒐集するきっかけになった。
世界旅行を楽しみながらの独楽探し 少年の夢かコマ数千点 服部雅夫
(株)萌文書林社長故服部雅生氏遺稿集「風知草」の中で私の事を読んだ歌。服部夫妻とは1995年スペイン旅行以来親交があり、独楽収集の協力者でもありました。現在も奥様には引き続き独楽収集に協力していただいております。
存分に遊びし独楽をふところに 昭和23年「松囃子」
中村雅樹著「橋本鵜二の百句」ふらんす堂より
子供が独楽で遊んだのである。しかし「存分に遊びし独楽を」と改めて表現されると、あたかも独楽が存分に遊んだかのような気もしてくる。自転する独楽だからこそ、このように受け取ることもあながち不自然ではない。回り疲れ、遊び疲れた独楽が、ふところの中で安らいでいるような印象。独楽の本質に触れている面白い一句である。(中村雅樹)
*橋本鶏二(1907-1990)三重県伊賀市生まれ。(俳人、エッセイスト高浜虚子の高弟)
独楽廻る青葉の地上妻は産みに 金子兜太 金子兜太氏第一句集「少年」より
独楽しばし止めて夕焼富士を見よ 「今村甲子夫句抄」より
きちがいの少女なり独楽廻り澄む 孤児の独楽立つ大寒の硬き地に
枯野の中独楽宙とんで掌に戻る 西東三鬼
2017年12月25日角川ソフィア文庫より発刊された「西東三鬼全句集」より。
西東三鬼(さいとうさんき):明治33年~昭和37年岡山県出身の俳人:33歳で両親を失い兄のもとで日本歯科医専を卒業歯科医師となる。33歳で患者に誘われ俳句を始める。3年後には新興俳句の旗手となる。戦時下に詠んだ句が世情不安を煽ると弾圧(京大俳句事件)されるも戦後は現代俳句協会の創設や随筆執筆など多彩に活躍した。
西東三鬼 代表句 おそるべき君等の乳房夏来る
水枕ガバリと寒い海がある
独楽も目が廻ってバタリ倒れけり
小沢変哲
独楽は回るもの、そして倒れるもの。その倒れぶりをこれほど人間的に描いた句も少ない。独楽が目が回るなんて誰が思いつくだろうか。さながら小沢昭一が独楽を演じているかのようではないか。句集「俳句で綴る変哲半世紀」から。
四季長谷川櫂氏解説(読売新聞2017.1.10)
一月の死へ垂直な独楽の芯 高岡修
年の初めの「一月」を「正月」と呼ぶと、両者が与えるイメージは同じ月でありながら、ニュアンスはだいぶちがってくる。「正月」だと、かなり陽気でくだけた楽しいイメージを放つ。まさに年の初めの「めでたさ」である。ところが「一月」とすると、どこかしら年の初めの厳粛な緊張感を伴った寒々しさが感じられる。おもしろいと思う。それゆえに「一月の死」は考えられても、「正月の死」はちょっと考えにくい。この場合の「一月の死」は、さまざまな受け取り方が考えられるだろうが、私は「形而上的な死」という意味合いとして、この句がもつ時空を解釈したい。死、それとは対極的に勢いよく回る独楽は、まっすぐにブレることなく静止しているかのように勢いよく回っている。しかし、その垂直な芯はやがてブレてゆらいで、必ず停止するという終わりをむかえることになる。つまり死である。一月の「1」という数字と、回っている独楽の芯の垂直性とが重なって感じられるーーというのは読み過ぎだろうか? 明日で一月は終わる。同じ句集には、他に「春の扉(と)へ寝返りを打つ冬銀河」がある。『果てるまで』(2012)所収。(八木忠栄)
(増殖する俳句歳時記)より
たとふれば独楽のはじける如くなり 高浜虚子
この句は下重曉子著「この一句ー108人の俳人たち」の本に依れば、彼が河東碧梧桐(かわひがしへきごとう)の死(昭和12年)に対し弔句として贈ったものです。
角川書店「季寄せ」の独楽の項目の例句より。
おのが影ふりはなさんとあばれ独楽 上村占魚
独楽もすっかり郷愁の玩具となってしまった。私が遊んだのは、鉄棒を芯にして木の胴に鉄の輪をはめた「鉄胴独楽」だったが、句の独楽は「肥後独楽」という喧嘩独楽だ。回っている相手の独楽に打ちつけて、跳ねとばして倒せば勝ちである。「頭うちふつて肥後独楽たふれけり」の句もある。形状についての作者の説明。「形はまるで卵をさかさに立てたようだが、上半が円錐形に削られていて、その部分を赤・黄・緑・黒で塗りわけられている。外側が黒だったように記憶する。この黒の輪は他にくらべて幅広に彩られてあった。かつて熊本城主だった加藤清正の紋所の『蛇の目』を意味するものであろうか。独楽の心棒には鏃(やじり)に似た金具を打ちこみ、これは相手の独楽を叩き割るための仕組みで、いつも研ぎすまされている」。小さいけれど、獰猛な気性を秘めた独楽のようだ。ここで、句意も鮮明となる。「鉄胴独楽」でも喧嘩はさせた。夕暮れともなると、鉄の輪の打ち合いで火花が散ったことも、なつかしい思い出である。昔の子供の闘争心は、かくのごとくに煽られ、かくのごとくに解消されていた。ひるがえって現代の子供のそれは、多く密閉されたままである。『球磨』(1949)所収。(清水哲男)
翻訳の辞書に遊ばす木の実独楽 角谷昌子
句集の後書きによれば、作者は文部省関連事業のボランティアとして海外派遣に携わってきたという。語学に堪能な人のようだ。さて、この単語をどう翻訳すべきか。思案しながら、たまたま机の上にあった「木の実独楽(このみごま)」を辞書の上でまわしてみる。思案はあくまでも翻訳語の上にあるのだから、上手にまわそうというのではなく、なんとなくまわしながら的語を「ひねり出そう」というわけだ。翻訳の仕事ではなくとも、人は思案に行き暮れたときに、ほとんど無意識のうちに何か別の行為にはしる。頭を掻きむしっている昔の文士の戯画があるが、あれなどもその一つだ。掻きむしったところで、よい知恵の浮かぶ保証があるわけでもないけれど、とにかく何かせずにはいられない。それがだんだん「癖」になってくる。私の場合には、行き詰まると煙草を吸う。とくに吸いたくもないのに、いつの間にか口に銜えている。煙が立ち上っていると、心が落ち着いてきて次に進めるようである。煙草に火がついている時間は、ほぼ三分間くらいか。この時間はいつも一定しているので、ちょっと思考の息を整えるのには、私にはちょうどよい時間幅ということだろう。このデンで言えば、作者の癖は机上で何かを手にしては転がすこと。あるいは、掌中で何かを玩ぶことのようだ。「木の実」の季節が過ぎると、何を掌中にするのだろうか。『奔流』(2000)所収。(清水哲男)
勝独楽は派手なジャケツの子供かな 上野秦
季語は「独楽」で新年。凧(たこ)と並んで、正月の男の子の代表的な玩具だった。情景は喧嘩独楽で、同時に回して相手をはじき飛ばしたほうが勝ち。たまたま通りかかった作者が、勝負や如何にと眺めていると、勝ったのは「派手なジャケツの子供」だった。それだけの句であるが、ここには作者の「やっぱりね」という内心がのぞいている。むろん「派手なジャケツ」は親に着せてもらっているのだけれど、その子供がその場を仕切る、ないしは支配する雰囲気とよくマッチしていて、「やっぱりね」とつぶやくしかないのである。こういう子供はよくいるものだし、私が子供だったころにもいた。そして面白いのは、この子に支配された関係が、大人になってもつづいていくことだ。クラス会などで出会うと、職業も違い、住んでいる場所も離れていてすっかり忘れていたのに、会った途端から、すうっと昔の関係に戻ってしまう。思わずも、身構えたくなったりする。これは、どういうことなのか。作者はおそらく、そうした未来の関係をも見越した上で、詠んだのではないだろうか。「派手なジャケツの子供」は一生涯派手にふるまい、地味で負けてばかりいる子供は、一生ウダツが上がらない。と、ここまで言うと極端に過ぎようが、しかし、子供のころに自然にできあがった関係は、なかなか解消できるものではないだろう。自分の子供時代を振り返ってみると、いちばんよくわかるはずだ。『佐介』(1950)所収。(清水哲男)
山の子が独楽をつくるよ冬が来る 橋本多佳子
独楽は新年の季語だが、ここでは「冬が来る」のだから「立冬」に分類する。文字どおりの「山の子」であった私には、思い当たる句だ。山国への寒さの訪れは早い。いかな「山の子」でも、この季節になると山野を駆けめぐるなどの遊びはしなくなる。遊び場を、室内に切り替えるのだ。女の子はお手玉遊びをやっていたようだが、男の子は独楽回しに熱中した。農家には土間がある。そこで回す。村の万屋(よろずや)には出来合いの独楽も売ってはいたけれど、誰も買わなかった。もっと安い鉄の心棒と輪だけのセットを買ってきて、本体は小刀で丹念に木を削って作った。仕上げるのには、何日もかかった。ただし、作者が見たのはもっと素朴な独楽づくりの様子だったのかもしれない。木の実に爪楊枝のような細い木をさすものとか、丸い厚紙にマッチ棒の心棒をさすだけのものとか……。そういうものも作ったが、やはり鉄の心棒と輪とで作った独楽は頑丈だったし、互いにはねとばしあう遊びもできたので、なんだか知らないが「ホンカクテキ」だと思っていた。おかげで、いまでも独楽はちゃんと回せる。もはや、淋しい技術に成り果ててはいるけれど。(清水哲男)
木の実独楽ひとつおろかに背が高き 橋本多佳子
橋本多佳子は女性にしては長身だったらしい。たくさんの木の実独楽の中でひとつだけ細長い奴がいて、回すと重心も定まらずすぐ止まってしまう。うまく回らない木の実独楽がすなわち自分だと多佳子は言っている。「愚かな自分」に向ける目は自己戯画化。大正期以来、虚子のもとで花開いた女流俳人の特徴は、良妻賢母自己肯定型か、育ちの良さ強調のあっけらかん写生派か、男が可愛いと思う程度のお転婆派に分類できる。それは男社会から見た理想的女性像の投影そのものであった。そして官僚や軍人高官、資産家の妻や娘が女流の中心にいた。もっとも詩歌に「興ずる」のは、そういう階層の人たちという社会通念もあった。多佳子も例に洩れず九州小倉の資産家の妻。大正時代に虚子を知り「ホトトギス」に投句。杉田久女に手ほどきを受け、後に山口誓子に師事する。久女の「自分」に執着する態度と誓子のロマンが、それまでの女流にないこの句のような「自己認識」を作り出したように思う。この句と同様背が高いことについての屈折した感情を詠った句に、飯島晴子の「寒晴やあはれ舞妓の背の高き」ある。背の高い哀しみはあるにせよ、舞妓である分だけ晴子の「あはれ」は美的情緒があり華麗。多佳子の「おろか」はナマの自分の肉体に向けられていて赤裸々である。『紅絲』(1951)所収。(今井 聖)
負独楽は手で拭ふき息をかけて寝る 加藤楸邨しゅうそん
強くなれよと独楽におまじないの息を吹きかけて眠りにつく子供を表現した歌。吉野せいの著作集「洟(はな)をたらした神」(弥生書房)によると昭和初めの子供達は、独楽が回転して不動に見える状態を「澄んだ」と呼んでいた。
梵鐘ぼんしょうの下の三和土たたきや独楽廻す 大木さつき
お寺の鐘楼は鐘を撞く人が朝夕踏み固めるので梵鐘の下は石のように固くなっている。独楽を回すのに恰好の場所。三和土(たたき)とは叩いて固めた土地。
むき出しの闘志のありて独楽の紐 渡部節郎
「むき出しの闘志」とはギラギラした言葉。もちろん独楽を回している子供の一人にみなぎっているのだが、独楽にも紐にも乗り移ったかのようではないか。しゅるしゅると紐を振りほどいては、次々にほかの独楽を弾き飛ばしてゆく。
四季長谷川櫂氏解説(読売新聞2010.1.8)
独楽童子ふところに手をあたためつ 黒川龍吾
着物に半纏を羽織ったハナタレ小僧のシモヤケで赤くなった手を彷彿させる。
独楽回す空き地に草も生えにけり 城正史
正月も終わろうとする頃には、はや春の息吹きを感じる様がいい。
独楽2つ触れてかなしも地の上に 廻り澄みつつ触れてかなしも 北原白秋
「かなし」にあてる漢字はいくつかある。「哀し」「悲し」「愛し」。少しずつ意味合いが異なるが、「かなし」という大和言葉はそのすべてを含んでいるのだろう。哀しくて悲しくて愛しい。いま白秋の前で回っている2つの独楽もまた。
四季長谷川櫂氏解説(読売新聞2011.1.16)
