実存と思想
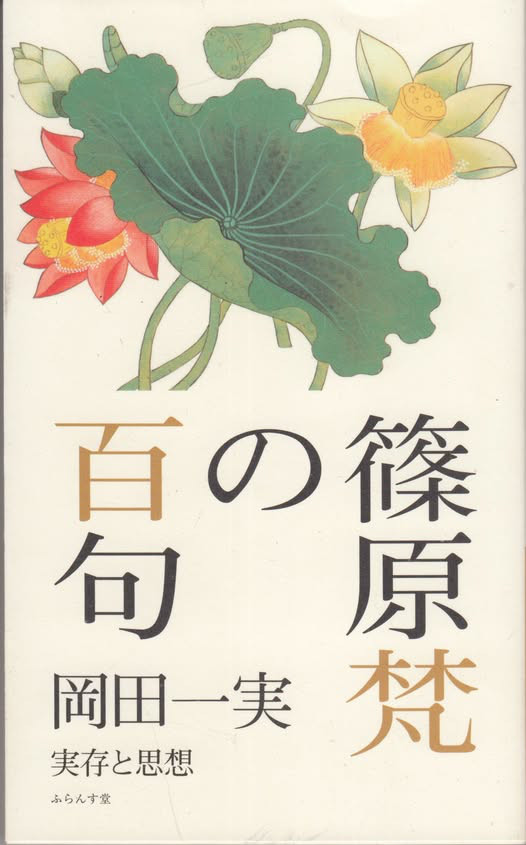
https://www.nhk.or.jp/meicho/famousbook/48_jitsuzon/index.html 【サルトル「実存主義とは何か」】より
第二次世界大戦後の世界にあって、常にその一挙手一投足が注目を集め、世界中に巨大な影響を与え続けた20世紀最大の哲学者ジャン=ポール・サルトル。彼の思想は「実存主義」と呼ばれ、多くの人々に生きる指針として読みつがれてきました。そのマニフェストであり入門書といわれているのが「実存主義とは何か」です。
「実存主義とは何か」は1945年10月、パリのクラブ・マントナンで行われた講演がもとになっています。この講演には多数の聴衆が押しかけ中に入りきれない人々が入り口に座り込んだほどだといわれます。翌日の新聞には大見出しで掲載され大きな「文化的な事件」として記録されました。その後、この講演は世界各国で翻訳・出版され一世を風靡し、時ならぬサルトル・ブームを巻き起こしました。サルトルの思想はなぜそこまで人々を魅了したのでしょうか。
大戦直後のヨーロッパでは、戦前まで人々を支えてきた近代思想や既存の価値観が崩壊し多くの人々は生きるよりどころを見失っていました。巨大な歴史の流れの中では、「人間存在」など吹けば飛ぶようなちっぽけなものだという絶望感も漂っていました。そんな中、「人間存在」の在り方(実存)に新たな光をあて、人々がさらされている「根源的な不安」に立ち向かい、真に自由に生きるとはどういうことを追求したサルトルの哲学は、人間の尊厳をとりもどす新しい思想として注目を浴びたのです。
若い頃サルトル思想の洗礼を受け大きな影響を受けたというフランス文学者、海老坂武さんは、既存の価値観が大きくゆらぐ中で、多くの人々が生きるよりどころを見失いつつある現代にこそ、サルトルを読み直す意味があるといいます。サルトルの思想には、「不安への向き合い方」「社会との向き合い方」「生きる意味の問い直し」など、現代人が直面せざるを得ない問題を考える上で、重要なヒントが数多くちりばめられているというのです。
番組では海老坂武さんを指南役として招き、入門書といわれながらも難解で手にとりにくい「実存主義とは何か」を、小説の代表作「嘔吐」や後期思想を交えながら、分り易く解説。サルトルの思想を現代社会につなげて解釈するとともに、そこにこめられた【自由論】や【他者論】、【社会への関わり方】などを学んでいきます。
川口覚さんからのメッセージ
今回のお話をいただいてから、J.Pサルトルという人物と僕が頭の中で向き合うのですが、J.Pサルトルの物に対する着眼点や、想像力に圧倒されてしまいました。でもそれと同時に、とても興味深く、どんどん引き込まれている自分がいました。海老坂先生の解説とともに、ぜひJ.Pサルトルを知っていただきたいです。決して過去の人物ではなく、今の時代を生きる人たちの心を動かす何かがあるはずです。
第1回 実存は本質に先立つ
【ゲスト講師】海老坂武(フランス文学者) …サルトル研究の第一人者。著書に「サルトル」(岩波新書)。 サルトルの訳書多数。
【朗読】川口覚…俳優。蜷川幸雄演出による7代目ハムレットで注目を集めた若手実力派俳優。
第二次世界大戦という未曾有の経験によって、既存の価値観が大きくゆらいでいたヨーロッパ。人々は、たよるべきよすがを失い「根源的な不安」に直面していた。意味や必然性を剥ぎ取られ不条理にさらされたとき、人は一体どう生きていったらよいのか? サルトルは、その「根源的な不安」に向き合い乗り越えるために、「実存主義」という新たな思想を立ち上げた。「人間の本質はあらかじめ決められておらず、実存(現実に存在すること)が先行した存在である。だからこそ、人間は自ら世界を意味づけ行為を選び取り、自分自身で意味を生み出さなければならない」と高らかに宣言した講演「実存主義とは何か」は、その後世界中で著作として出版され、戦後を代表する思想として広まっていた。その第一回は、「実存主義とは何か」が生み出された背景やサルトルの人となり、デビュー小説「嘔吐」も合せて紹介しながら、現代にも通じる「根源的な不安」への向きあい方を読み解いていく。
第2回 人間は自由の刑に処せられている
世界や存在にはそもそも意味はない。だがだからこそ人間は根源的に「自由」なのだ。人間の根源的条件をそう考えたサルトル。だがそれは同時に人間に大きな不安を与えるものでもある。自分自身があらゆる行動の意味を決めなければならないからだ。そこには絶対的な孤独と責任が伴う。その状況をサルトルは「我々は自由の刑に処せられている」と表現した。人間はともするとこの「自由」に耐え切れず「自己欺瞞」に陥ってしまう。第二回は、「実存主義とは何か」や小説「嘔吐」から、人間にとっての「自由」の意味を読み解き、どうしたらその「自由」を本当の意味で生かしきることができるかを考える。
https://www.nhk.or.jp/meicho/famousbook/48_jitsuzon/guestcolumn.html 名著、げすとこらむ。対話者としてのサルトル」より
サルトルは一九八〇年四月十五日、七十四年有余の生涯を閉じました。それを知ったのは日本時間で四月十六日の朝七時のNHKのラジオのニュースによってです。そのとき私はたまたま、彼の最後のメッセージとなった「いま 希望とは」というインタヴュー記事を「朝日ジャーナル」という週刊誌の依頼で翻訳をしている最中でしたが、その翻訳を投げ出したくなる程の喪失感にとらわれたことを覚えています。そしてその四半世紀前、大学に入ってしばらくして『嘔吐』という小説をなんとか読み終え、サルトルの研究者になろうと決意したときのこと、またその後十年ほどしてローマの街角でばったり出会い、思わず話しかけたこと、そしてその後三回、直接話を聞くことができたことなどを思い出していました。
しばらくすると、フランスの新聞や雑誌が届き、サルトルの死がかの地でどのように迎えられたかを、驚きと共に知ることになりました。彼の葬儀の日にパリで、なんと五万人の人々が病院からモンパルナスの墓地まで遺体が運ばれる沿道に並び、最後の別れを告げたというのです。
その中にこんなエピソードを伝えている新聞もありました。病院で出棺の際に、詰めかけた人々に、葬儀屋が「ご家族の方は前に出て下さい」と声をかけたところ、一人の女性がこう叫んだというのです。「私たちみんなが家族です!」
この一つの声がどれだけの人々の想いを代弁していたかはわかりません。しかしこういう声が群衆の中からとっさに発されたということは、サルトルという人の意味を考える上で無視されていいことではないでしょう。その声はいかなるサルトルに向けられていたのか。いかなる点で彼女は自分をサルトルの「家族」と考えたのか。またこの日街頭に出てサルトルに別れを告げ、あちこちのカフェで夢中になってサルトルの話をしていたという多くの人々にとって、サルトルとは何者だったのでしょうか。
ジャン゠ポール・サルトルは、哲学者であり、小説家であり、劇作家でもあります。彼は思想と文学の様々なジャンルにわたって、厖大な著作を残しました。『嘔吐』『存在と無』『自由への道』『聖ジュネ』『アルトナの幽閉者』『弁証法的理性批判』『家の馬鹿息子』、どの作品も二十世紀フランスの文学、思想の歴史に大きな足跡を残しています。
しかし、葬儀の日、パリの街頭に繰り出した五万の人々が想いを寄せていたのは、こうした作品の著者としてのサルトルではなかったのではないか。いや、正確に言うなら、そういうサルトルだけではなく、もう一人のサルトル、同時代の人々が、「この問題について、あの人はどう考えているだろうか」と問いかけ、自分が答えを出すための対話相手としてきた「あの人」としてのサルトルではなかったか……そんな風に考えます。
実際、サルトルは、インドシナ戦争、朝鮮戦争、ローゼンバーグ事件、原水爆実験、ソ連の強制収容所、アルジェリア戦争、ハンガリー動乱、ド・ゴールによる権力奪取、アラブ−イスラエル紛争、プラハの春、ヴェトナム戦争、五月革命、ボートピープル……二十世紀の歴史、戦争と革命と植民地解放の世紀の歴史を引き裂くこれらの出来事に対して常に旗幟を鮮明にしてきました。同時代のフランスの作家であるアンドレ・マルローもアルベール・カミュもルイ・アラゴンもそれぞれの立場で態度表明をしていたのですが、サルトル以上に社会にインパクトを与えた人はいなかったはずです。
一人の作家の発言に多くの人が耳を傾ける、こういうことが可能であったのは、理のある言葉を尊重する、理のある言葉に力を持たせる、というフランス社会の伝統があったことも見逃してはならないでしょう。そこから、冤罪で死刑になったジャン・カラスの再審運動を展開して裁判を勝ち取ったあのヴォルテール、ナポレオン三世のクーデタに抗議して亡命し、十九年間、詩作品をとおして専制体制を弾劾し続けたあのヴィクトル・ユゴー、スパイ容疑で裁かれたドレフュス大尉の無罪を訴え続けたあのエミール・ゾラのような大知識人も生まれてきたのです。
こうしたサルトルの発言の多くは直ちに日本にも伝えられ、少なからぬ影響をもたらしました。一九五〇年代末から一九七〇年代にかけての安保闘争、ヴェトナム反戦運動、大学闘争などにかかわった方々なら─―もうすでにかなり年配の方々になりますが─―この時代のサルトルの言葉のあれこれを記憶の片隅に留めておられるかもしれません。また一九六六年にボーヴォワールと二人で来日したときの東京と京都とでの講演会には、会場に入りきれない人が詰めかけ、講演内容はすぐに新聞や週刊誌に報道され、知識人論議をまきおこすことになりました。
もちろん、今日の観点からするなら、サルトルの発言や取った立場がすべて正しかったとは言えない。とりわけソ連の社会主義にたいして抱いていた期待は、今の時点から見ると幻想と言われても仕方がないでしょう。考えてみると二十世紀というのは決して幸福な時代ではなかった。この世紀ほど大量に人間が人間を殺し、人間が人間を監禁した時代はない。一方で人間解放の運動が大規模に繰り広げられながら、他方で人間抑圧、人間疎外が深く進行して、歴史の流れが数々の希望を押し流し、幻想に終わらせてしまった世紀でした。
その中で「もっといい時代はあるかもしれないが、これがわれわれの時代であり、作家は自分の時代と一つになるべきだ」という自分の言葉をサルトルは愚直なまでに生きていた。若き日の友人だった哲学者のレーモン・アロンのように時代の「観察者」の位置には決して立たず、持続的に精力的に、同時代人にメッセージを発し続けた。一九六八年の五月革命の世代の若者たちは「アロンと共に正しくあるよりは、サルトルと共に誤ることを選ぶ」としてこうしたサルトルの姿勢を支持したのですが、それは、傍観者の正しさとは単なる日和見主義にすぎぬことを見抜いていたからで、たとえ誤ったにしても、サルトルのうちに、同時代のかけがえのない対話者を見ていたからではないでしょうか。私はそう考えます。
では、いま二十一世紀に生きる私たちにとってはどうでしょう。世紀は新しいページをめくって十五年になります。二十世紀の大知識人サルトルはもはや時代遅れの過去の人なのでしょうか。私にはそうは思えません。「自分とは何か」「他人とは何か」「社会にいかにかかわるべきか」等々、誰でも立ち止まって自分の人生について考えるときがあるはずです。そんなときサルトルという人は、確実に私たちの対話者になってくれると考えるからです。
この放送では『実存主義とは何か』を入り口にして、サルトルの実存主義の原点ともいえる小説『嘔吐』を中心に、哲学書『存在と無』など、他の作品の紹介もするつもりです。加えてサルトル自身の人生や、その思想と行動の変遷についても触れながら、実存主義がいかにして「希望の哲学」を語るようになっていったかを多角的に探っていくつもりです。ただ今回のテキストでは、サルトルの全体像は語りえないので、私なりの「実存主義入門」もしくは「サルトル入門」だと思っていただければ幸いです。
第3回 地獄とは他人のことだ
決して完全には理解し合えず相克する「他者」との関係。だが、その「他者」なしには人間は生きていけない。「他者」と相克しながらも共生していかなければならない状況をサルトルは「地獄」と呼ぶ。こうした根源的な状況の中で、人は「他者」とどう向き合ったらよいのか? 第三回は、自分の「自由」の前に立ちはだかる「他者」という「不自由」を見つめ、主体性を失うことなく「他者」と関わりあうことがいかにして可能かを、サルトルの思想に学んでいく。
もっと「実存主義とは何か」https://www.nhk.or.jp/meicho/famousbook/48_jitsuzon/motto.html
ほらね、君が現象学者だったらこのカクテルについて語れるんだよ、そしてそれは哲学なんだ!」(シモーヌ・ド・ボーヴォワール「女ざかり」 朝吹登水子訳)
サルトルが、自らの哲学の基礎となる「現象学」という哲学的方法に出会った瞬間を生き生きと描写したシモーヌ・ド・ボーヴォワール「女ざかり」の一節です。今回の番組では紹介しませんでしたが、サルトルのその後の哲学を象徴するようなエピソードなので、以下、少し長めですが、引用させてください。
レーモン・アロン(※注 フランスを代表する社会学者)はその年をベルリンのフランス学院で送り、歴史の論文を準備しながらフッサール(※注 現象学を創始した20世紀を代表するドイツ哲学者)を研究していた。アロンがパリに来た時、サルトルにその話をした。私たちは彼とモンパルナス街のベック・ド・ギャーズで一夕を過ごした。その店のスペシャリティーであるあんずのカクテルを注文した。アロンは自分のコップを指して、
「ほらね、君が現象学者だったらこのカクテルについて語れるんだよ、そしてそれは哲学なんだ!」サルトルは感動で青ざめた。ほとんど青ざめた、といってよい。
それは彼が長いあいだ望んでいたこととぴったりしていた。つまり事物について語ること、彼が触れるままの事物を……そしてそれが哲学であることを彼は望んでいたのである。アロンは、現象学はサルトルが終始考えている問題に正確に答えるものだといってサルトルを説き伏せた。つまりそれは彼の観念論とレアリスムとの対立を超越すること、それから、意識の絶対性とわれわれに示されるままの世界の現存とを両方同時に肯定するという彼の関心をみたすのだとアロンは説得したのであった。
(シモーヌ・ド・ボーヴォワール「女ざかり」 朝吹登水子訳)
…いかがですか?まさに興奮の瞬間でしょ?サルトルの哲学って、実は、モンパルナスのカフェで生まれたんですね。
「哲学」というと、どうしても浮世離れしているイメージがあり、自分たちの普段の生活や仕事には直接関係ない、ちょっと抽象的で難しくて近寄りがたい存在…だ、と思いがちですが、そんなイメージを吹き飛ばしてくれたのがこの一節でした。高校時代、この一説に触れて、「え?カクテルについての具体的な経験をそのまま語れるような哲学があるの?」と衝撃を受け、現象学やサルトルの哲学に猛烈に引き込まれていった…というのが私自身の哲学初体験。初めて書店に注文して手にした哲学書が「実存主義とは何か」でした。
すでに番組に触れていただいた方々には、その手触りをわかっていただけると思いますが、サルトルは徹頭徹尾、私たちの「具体的な生」について語っています。もちろん難解な用語はたくさん出てはきますが、サルトルはまるで、カフェで今まさに手にしているあんずのカクテルを語るかのように、私たちが「いかに生きるべきか」「社会とどう向き合うべきか」について問いかけてくれているように思えるのです。サルトルがここまで多くの人たちの心をつかんだのは、こうした「具体性」にあったのではないかと、今回の番組制作を通して、あらためて思いました。
サルトルは「忘れ去られた哲学者」ともいわれ、存命中にあれだけの影響力をもったにもかかわらず、今ではほとんどその著作を手にとる人はいなくなってしまいました。ですが、サルトルが格闘した問題や、それに対する彼のメッセージは決して古びてはいないと思います。サルトル哲学の可能性はまだまだ汲みつくされていないのです。この番組をきっかけに、あらためてサルトルを読み直してくださる方が少しでも増えることを祈っています。
(略)
第4回 希望の中で生きよ
人間は根源的に与えられている「自由」をどう生かしていけばいいのか。サルトルは「実存主義とは何か」で、「アンガージュマン」(参加・拘束)という概念を提唱し、人間は積極的に《状況》へと自らを《投企》していくべきだと訴える。社会へ積極的に参加し、自由を自ら拘束していくことが、自由を最も生かす方法だと主張するのだ。それは、サルトルが生涯をかけて、身をもって実践した思想でもあった。第四回は、「実存主義とは何か」だけでなくサルトルの具体的な実践や後期思想も交えながら、どんなに厳しい状況にあっても「自由」を生かし、「希望」を失わずに生きていく方法を学んでいく。
こぼれ話。
サルトルとともに……
あまりにも痛ましかったパリ同時多発テロ。犠牲になった方々のこと、そして、ご遺族の方々のことを思うと胸が張り裂けそうになります。とともに、非道な暴力に対する強い憤りを禁じえません。
今回取り上げたジャン=ポール・サルトルの活動拠点もパリでした。番組の最終回をあらためてかみしめつつ、今回の事件に対してサルトルだったらどのような発言をしただろう……という思いが去来しました。
講師の海老坂武さんは、サルトルについて「時代の対話相手だった」と語っていました。何か起こるたびに、サルトルは果敢に自らの主張を発信し、態度表明を続けました。彼に反対にするにしろ、賛成にするにしろ、人々は彼がどんな意見を述べるかに注目をしました。サルトルの思想は、ある時代の「座標軸」となっていたのかもしれません。そんな彼が今、生きていたとしたら?
サルトルほど戦争を憎んだ知識人は稀だったのではないか。そして、サルトルほど、傷つけられた人たち、虐げられた人たち、抑圧された人たちと連帯し、行動した作家は当時いなかったのではないか。学生時代、夢中でサルトルを読み続けた私の実感です。
そんなサルトルならば、おそらくまず何よりも、無辜の民を無差別に虐殺するようなテロリズムを断固糾弾したことでしょう。しかし、彼はそこにとどまらないような気がします。返す刀で我が身をも切り裂いたのではないか? テロリズムは絶対に赦されるべきではない。しかし、一方で、そのテロリズムが生み出される根本原因にメスを入れなければ何の解決も得られない。その原因の一端は我が身の内にある。西欧社会の側にもある。そういって、自らの血を流すような鋭い論評を行ったのではないか? 「シチュアシオン」という彼の膨大な発言集を紐解くと、そんなことを髣髴とさせる場面に何度もぶちあたります。
「民間人を巻き込んでしまうような空爆が果たして許されるのか」「テロリズムとどう対峙していけばいいのか?」「憎しみの連鎖はどうやったら断ち切れるのか」「難民の受け入れをどうしていったらよいのか」「民族間、宗教間の差別感情、憎悪の感情とどう向き合ったらよいのか」等々、今、私たちは、そう簡単には答えを出せない多くの問題に直面しています。
それでも、私たちは、問い続けなければならない。そして何らかの答えを見つけなければならない。そんなときに、サルトルの著作は、少なからずヒントを与えてくれるような気がします。
私は、今年九月、番組制作の報告をかねて、サルトルの墓前で手を合せてきました。
サルトルとボーヴォワールの墓
その場所で、思い出されてならない言葉がありました。番組でも紹介した、サルトルの最期の言葉といってもいい言葉です。
「世界は醜く、不正で、希望がないように見える。といったことが、こうした世界の中で死のうとしている老人の静かな絶望さ。だがまさしく、私はこれに抵抗し、自分ではわかっているのだが、希望の中で死んでいく。ただ、この希望、これをつくり出さなければならない」
(対話「今、希望とは」より)
どんなに厳しい状況にあっても、サルトルとともに、「希望」を語り続けたいと思います。
facebook西尾仁さん投稿記事
いつか死ぬからこそ、今を精一杯生きることが必要なのです。大切なのは、自暴自棄になったり、くよくよ思い悩んだりせずに、与えられたその日、その場に精一杯取り組むこと。
過去を思い煩わず、明日を思い悩まず今に全力投球するべきなのです。
生きるということは、寿命という器の中に、精一杯生きた一瞬一瞬の時間をを詰め込んでいくことです。その時間の質を決めるのは、あなた自身です。
一瞬一瞬の時間を、もっと意識して、もっと大事にして、精一杯生きていきましょう。
一生は、今この一瞬の積み重ねの時間です。いのちも時間も目には見えないけれど、時間を使うことでいのちが形になります。
自分のいのちである自分の時間を有意義に使う。そして、是非、いのちの時間を自分のためだけでなく、人のためにも使ってください。日野原 重明Good Day!!
